矯正歯科コラム
COLUMN開咬の治療について
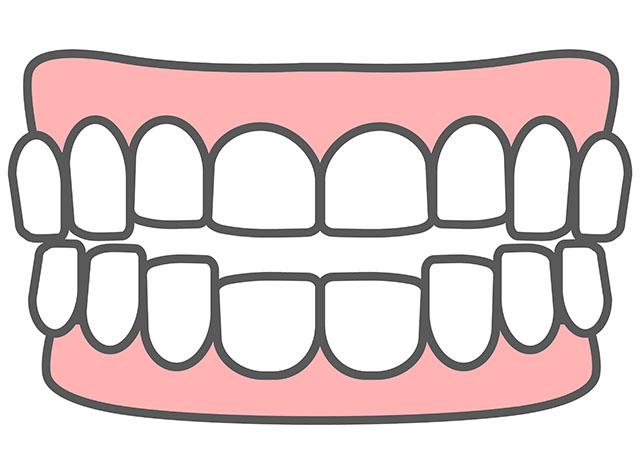
開咬(かいこう)とは、上下の前歯が噛み合わずスペースが開いている状態のことで、オープンバイトとも呼ばれます。今回は、開咬の原因や主な症状、治療方法について解説します。
◎開咬の原因と主な症状
開咬の原因はおもに3つあります。まずは、それぞれについて詳しくみていきましょう。
【舌癖】
開咬の原因においてもっとも多いとされるのが、舌の癖です。子どもの頃からの頑固な指しゃぶりや、舌を歯で咬む癖などによって、持続的に前歯に力がかかって開咬になることがあります。
【口呼吸】
鼻炎や扁桃腺肥大、蓄膿症などによって慢性的に鼻がつまっていると、口呼吸の習慣がついてしまいます。口呼吸を続けていると、口腔の筋肉のバランスが崩れ、舌が歯列の正しい位置に収まらなくなります。これが原因で開咬となる場合があります。
【骨格】
下顎の成長不全、顎関節の変形など、骨格的な問題が開咬を引き起こしていることがあります。
【歯の生え代わり】
歯の生え代わりがスムーズにできず、これが原因で開咬になることがあります。
開咬の方にみられる症状としては、「前歯で食べ物を咬むことができない」、「食べ物が口からよくこぼれる」、「舌足らずな発音になる」などが挙げられます。
◎開咬を放置するリスク
開咬の方は前歯をうまく使えないことから、奥歯への負担がかかりやすくなります。そして過度な力が加わり続けた歯や骨は寿命が短くなりやすいため、歯を早くに失ったり、歯周病の進行を早めたりするおそれがあります。また、歯は食べ物を噛み砕いて消化を助ける働きがありますが、開咬ではそれが十分にできません。放置しておくと嚥下障害や胃腸障害を引き起こすことがあります。口呼吸を伴うケースでは、口腔の乾燥によって虫歯や歯周病のリスクが高まったり、風邪などの病気にかかったりする可能性が高くなります。
◎開咬の治療方法
開咬は、ブラケットを装着したワイヤー矯正装置、またはマウスピース型矯正装置による歯列矯正で治療できます。前歯を倒し込む、または奥歯を沈み込ませる方法で、歯列を整えていきます。ただし、舌の癖を原因とする開咬は、矯正後に後戻りしやすいとされています。根本的な解決を目指すために、舌先や口の筋肉のトレーニングによって舌癖を改善するMFT(口腔筋機能療法)を同時に進めることもあります。
記事監修 深谷矯正歯科 院長 深谷哲郎

■略歴
- 1988年3月 栃木県立真岡高等学校卒業
- 1994年3月 北海道大学歯学部卒業
- 1994年4月 東京医科歯科大学歯学部第2矯正科入局
- 1998年4月 東京医科歯科大学歯学部第2矯正科医員
- 1999年4月 赤坂まつの矯正歯科非常勤勤務
- 2001年4月 ふかや矯正歯科開院
- 2003年4月 船橋市立行田東小学校学校歯科医
■所属学会
